クリニックの新規個別指導・監査とは?
医療機関が厚生局から聞かれること
【更新日】2023/12/28
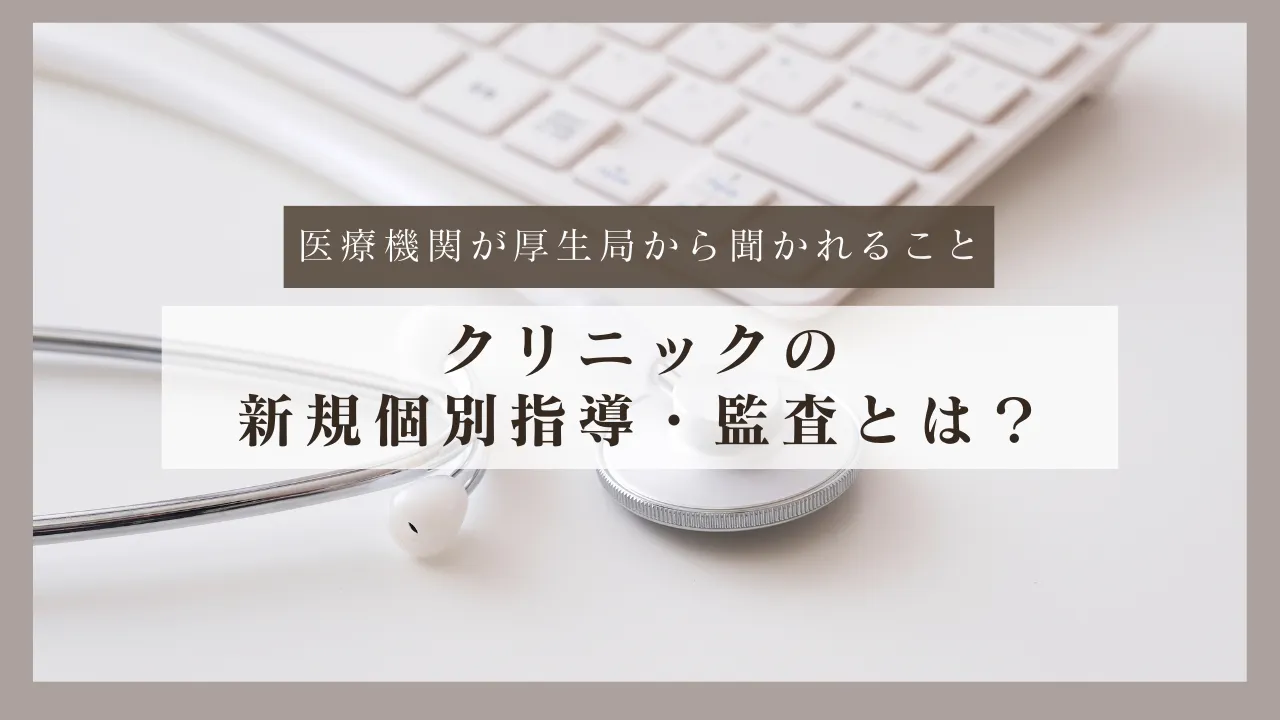
全国の病院、診療所に対しては継続して行政指導が行われています。
開業された先生の中には医療機関に対する個別指導・監査について聞いたことがある、または実際に個別指導を受けたことがあるというかたもいらっしゃるでしょう。
今回はこれから開業される先生や、すでに開業されている先生に対し、この個別指導・監査とはいったいどんなものなのか、また実際に厚生局から聞かれることはどんなことがあげられるかをご紹介していきます。
個別指導の概要と対応を把握し、リスクを回避するためにも診療所でできる対策を確認しておきましょう。
個別指導とは?
個別指導というのは厚生局が医療機関、保険医に対して、保険診療や診察費請求を適切に行うように指導を行うものです。
健康保険法第73条、国民健康法第41条などにおいて、医療機関や保険医はこの指導を受ける義務があることが定められています。
参考
個別指導の分類
個別指導にはいくつか分類があり対象が異なっています。
- 新規個別指導
- 集団的個別指導の個別指導部分
- 患者や保険者からの情報提供により行われる個別指導
- 個別指導後の再指導
開業される先生にとって最も注目すべきは新規個別指導でしょう。
こちらは新規開業の医療機関に対して開院後おおよそ1年で実施される個別指導になります。
コロナ禍では新規個別指導が一時休止されていましたが、現在は以前のように実施されています。
この新規個別指導だけは避けられないため、開業された先生は開業後1年ほどで指導があることをあらかじめ心得、準備をしておきましょう。
個別指導の結果

個別指導の結果については以下4つに分かれます。
- 概ね妥当
- 経過観察
- 再指導
- 要監査
個別指導実施日より2〜3ヶ月後に、指導結果が郵送で届きます。
不正請求などが明らかになり要監査となった場合には結果に応じて「注意」「戒告」「取消」などの処分が下されます。
「取消」は保険医療機関、保険医としての指定の取り消しであり最大5年間保険診療ができなくなる重い処分です。
監査を受けることのないよう、また監査後に取り消し処分を受けることのないように、十分に注意しておきましょう。
新規個別指導の流れ
先にお伝えしたように、新規個別指導は開院後1年ほどで実施されます。
厚生局による個別指導の流れは以下のようになります。
1. 実施の通知、指導日の告知
指導日の1カ月ほど前にクリニックに個別指導の実施通知が送られてきます。
指導日の1週間前には20人分、前日の正午までに10人分の対象患者名が指定されます。
2. 個別指導当日
クリニックへの個別指導は厚生局の会議室で実施されます。
厚生局、また都道府県の職員、加えて医師会から派遣される立ち合い医師が参加します。
当日は指導日から6カ月前の連続した2カ月間の診療報酬明細に基づいて書類を閲覧され、面談方式で個別指導が実施されます。
指導はおおよそ1時間です。
ここで明らかな不正または不当が疑われますと、そのまま指導を中止、監査に移行することがあります。
ここで委任状を提出しての弁護士帯同をすることができますが、答弁については弁護士は行えず先生が行います。
3. 個別指導の結果と措置の通達
原則として1〜2カ月以内に個別指導の結果が通知されます。
注意すべきは「取り消し処分」
最も注意すべきは個別指導から監査へと移行した際に下されることのある、「取り消し」処分です。
取り消し処分は以下のような行為が確認された際に下されます。
- 架空請求:実際には診療を行っていないのに請求書を発行した場合、架空請求とみなされます。
- 二重請求:自費診療の診療費を患者から受領しているにもかかわらず、保険診療でも診療報酬を請求した場合、二重請求に該当します。
- 付増(つけまし)請求:診療回数や診療日数などが実際よりも多く請求されていると、付増(つけまし)請求とみなされます。
- 振替請求:保険診療内容を、実際の診療よりも保険点数の高い診療内容に振り替えて請求している場合です。
個別指導・監査によって取り消し処分を受けることのないようにするため、上記4点には特に注意しましょう。
故意に行っていなくとも、管理が甘かったために監査、取り消し処分を受けては悔やんでも悔やみきれません。
請求内容と金額の合致確認、経理や事務処理の確認、支払い記録とレセプトの照合などを徹底する必要があります。
ただし、これらをひとつずつ順番に照合していると大変な時間がかかります。
電子カルテで一元管理し、スムーズな確認ができる体制を敷いておくのが望ましいでしょう。
個別指導での指摘例
実際に個別指導を受けた先生から、具体的に下記のような指摘を受けたということを聞いております。
- 診療録における診療内容等の記載が乏しい
(※初再診のとき、「前回と同じ」でも良いので初診時に行う問診項目を記載する など) - 通称を使用しており、傷病名が正しくない
(※傷病名に症状は書かない など) - 診療時間や勤務医など変更事項の届出が未提出である
- 電子カルテのパスワード設定が定期的に行われていない
- 算定要件を満たしていない診療報酬の請求がある
- 電子カルテに加算要件の内容の記載がない
(※例:「特定疾患療養管理料」の場合であれば、服薬だけでなく運動や栄養指導も行った旨も記載する など)
その他、本来加算が取れる内容についてのアドバイスも受けたとのことでした。
このような点を指摘されないようにクリニックを運営していくことが大切です。
指導結果通知後の対応
ここでは、指導結果のうち約7割を占める「経過観察」となったときの対応について説明してまいります。
経過観察となると、指摘事項の改善報告書と返還金がある場合は返還金同意書等の提出が必要となります。
提出期限は、受け取り後、1ヶ月程度を目安に設定されていますので、余裕を持って提出できるよう準備を進めましょう。
改善報告書
指摘を受けた項目に関する改善報告を行う書類です。
基本的に簡単な内容で問題ありません。
同封されている記載例に沿って記載するようにしましょう。
返還金同意書等
返還金の対象となる方が国民健康保険の加入や、社会保険の加入かなどによって様式が異なるため、全ての様式の書類が送られてきます。
関東信越厚生局が管轄の医療機関であれば、関東信越厚生局ホームページ内の「返還金同意書等作成支援ツール」を用いると、簡単に書類を作成することができます。
半年〜1年間はレセプトをチェックされるので注意
経過観察は合格ではありません。
個別指導での指摘事項が改善されているかレセプトのチェックをされる点は注意しましょう。
とはいえ、結果が経過観察の医療機関で再指導となるケースはほぼありませんのでご安心ください。
なお、詳細は管轄の厚生局へご確認ください。
個別指導にむけて日頃からクリニック運営のマネジメントを徹底しましょう

個別指導は特に新規に開業した先生にとっては避けられないものです。
しかし急に案内をみて慌てるのではなく、開業後には新規個別指導があるものだということを踏まえておくだけでも心持ちは変わるでしょう。
また、日頃から診療録に祖語のないような意識をスタッフの皆さんに持っていただく、電子カルテなどをうまく活用してシステムとしてミスが起きにくい、現状を確認しやすい状態を整えておくことも重要です。






