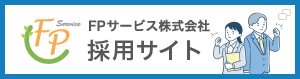経営に役立つ情報を毎月お届け!
ドクターサポート通信
Drサポート通信では、クリニック経営のヒントとなる情報をお届けしています。
医療機関や介護機関との連携で経営の光明は見出せるか
「疾病構造の変化」「患者ニーズの多様化」「医療技術・サービスの高度化」
「高齢化の進展」「医療・介護保険財政の逼迫」「医師・看護師・介護福祉士などの人材不足」
医療を取り巻く経営環境は厳しいものとなっています。
これらに対して個々で対応するには限界がありますが、なぜ医療機関同士、あるいは医療機関と介護事業者の連携が求められるのでしょう。
医療機関同士や医療機関、介護事業者連携は必要?

患者様の住む地域には多くの社会資源、医療資源、介護資源が存在しています。
医療連携、医療介護連携によりこれらの資源を有効活用し、患者様は疾病予防から治療、病後の介護・老後の介護まで切れ目のないサービスを受けることできます。
そのためには各診療所、病院が自らの機能を明確にすることが必要となります。
実際、国の医療・福祉政策も連携の強化へ向かっています。
更に診療報酬や介護報酬改正のたびに連携のレベルアップを促す政策や連携を後押しする報酬項目が相次いで実施されています。しかも、国は医療機関や病床、介護施設や介護サービスを機能別に区分し、この機能分化をフォローするために様々な連携促進策を講じています。
特に2009年の介護報酬改正では、医療機関との連携を評価した加算が新設されるなど、医療介護連携を後押しする政策が打ち出され、2010年診療報酬改正では、医療崩壊の阻止に向けた医療連携、医療介護連携が評価されるに至りました。
現政権下では先行きに不透明な感はありますが、国の連携重視・連携強化の方針に大きな変動がなく、今後も報酬改正などを活用して政策誘導する流れが続くものと思われます。
次回2012年は診療報酬改正と介護報酬改正のダブル改正の年であり、医療と介護に関わる部分が重点的に評価される可能性が高く、中でも当分の間凍結された「介護療養病床削減計画」の動向はポイントとなるでしょう。
また在宅患者や介護施設入所者などが急性増悪した場合の慢性期救急機能やクリニックに求められている「家庭医」機能や在宅医療の担い手としての機能の拡充評価される可能性も高いと言われております。
医療と介護に関わる領域の議論が活発に行なわれるようになった例をご紹介します。
- 社会保障審議会介護保険部会において、「介護療養病床」の転換先の選択肢を増やす案(特別養護老人ホームに新たな類型を設ける:転換型特養)
- 介護の必要度、医療ニーズ、家族背景などに応じて介護保険3施設の入所者像を明確化させる案
- 訪問看護と訪問介護などの複数サービスを、利用者ニーズに応じて一つの事業所から柔軟に提供できるようにする「複合型事業所」創設案
この様な状況を考慮すると連携の重要性を増してきたと言えますが、その目的はあくまで「患者や地域住民に質の高い効率的な医療・介護・福祉サービスを提供」であることを肝に銘じておく必要があります。
お互いの連携をWIN-WINの関係にするためには
- 連携の目的(患者のための連携であること)を受け止めること
- 相手機関の役割を理解すること
- 自らの機関の立ち位置を把握して、期待される役割を果たして行くこと
上記3点が留意事項となるでしょう。